コンテンツ
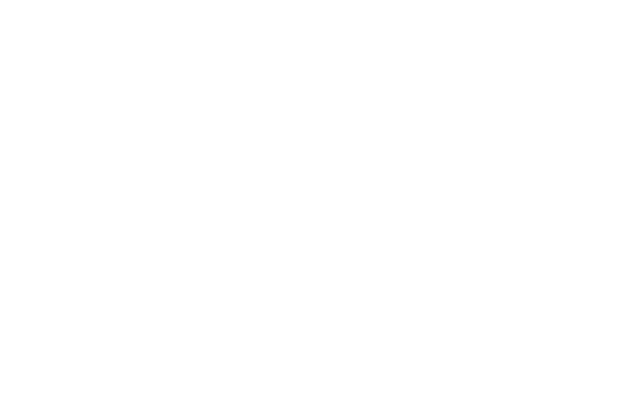
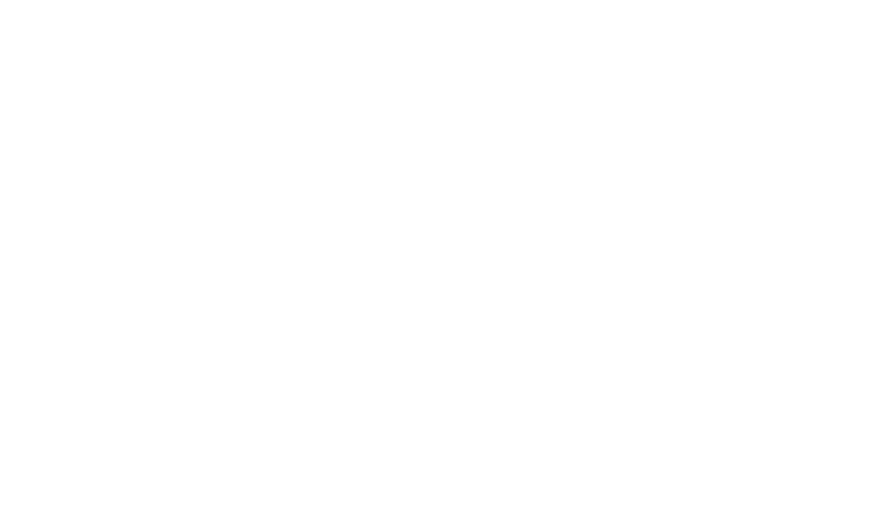
-
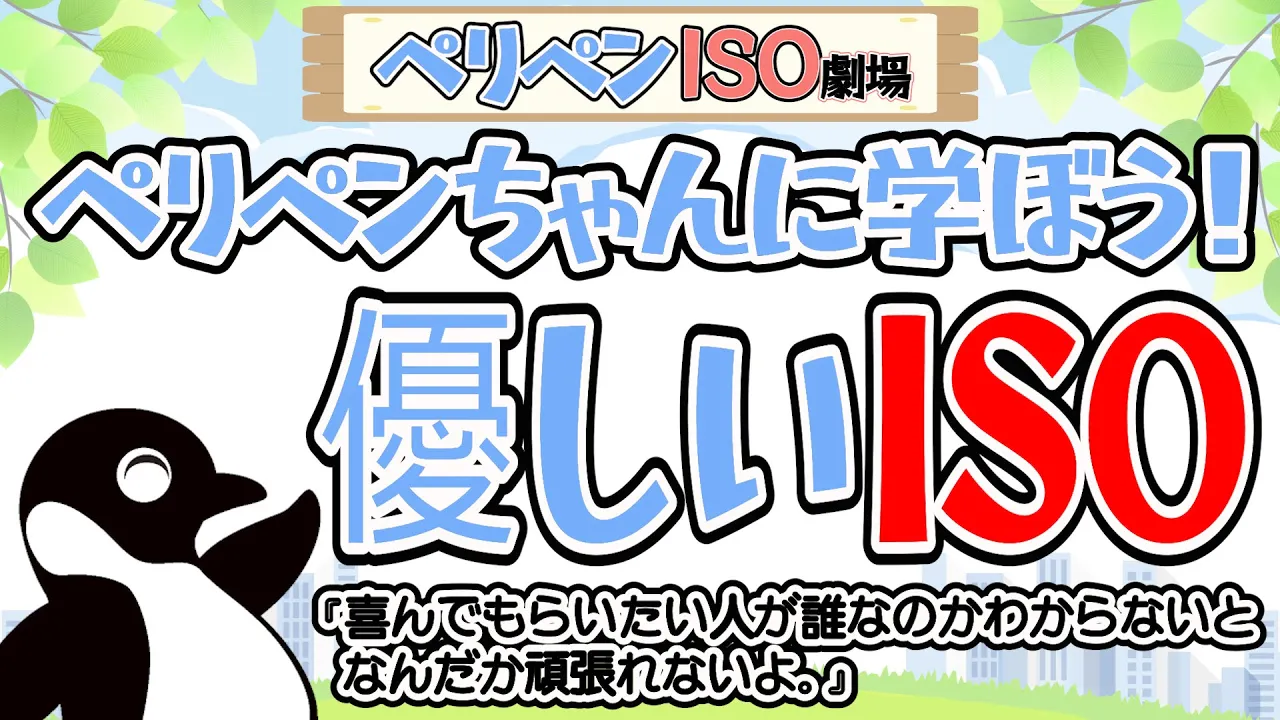
【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~顧客重視~」(全8回)
- 動画
-

【PJRの経営に効くISO】ペリージョンソン お客様感謝セミナー2021
- 動画
-
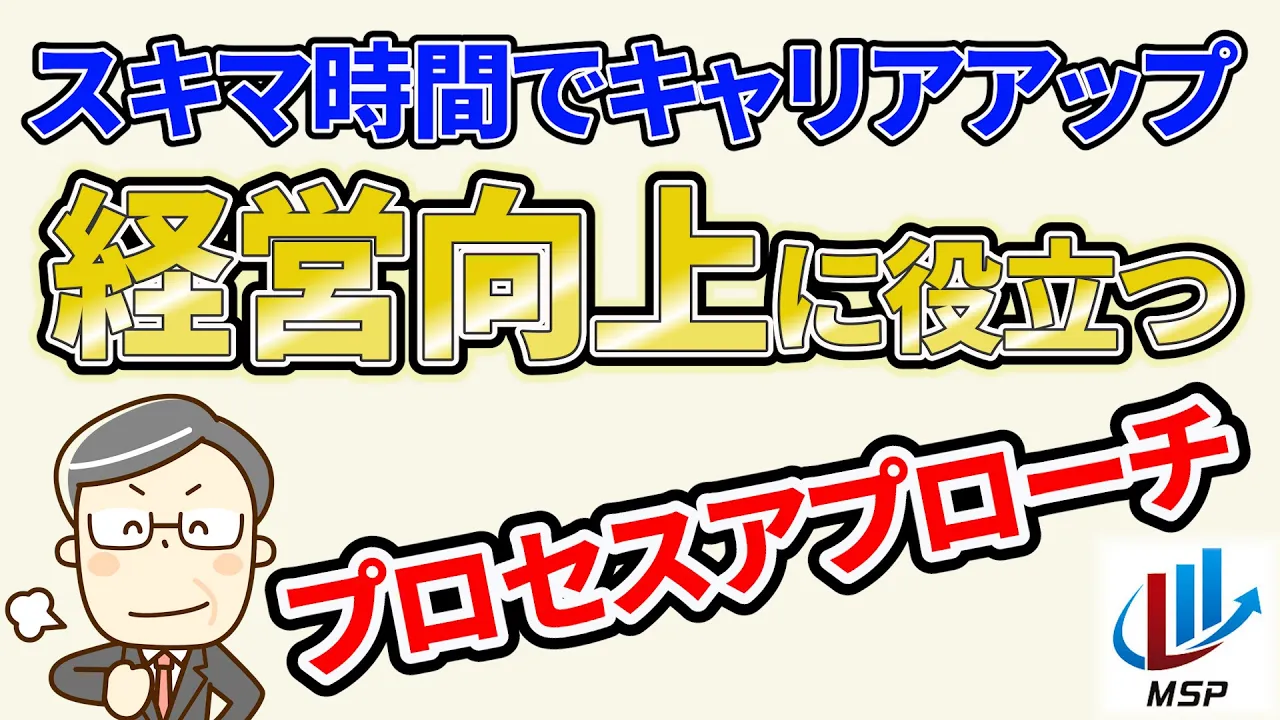
【MSP】2022年度マネジメントシステムパフォーマンス講座(全14回)
- 動画
-

【ISO】いまさら聞けない!ISO基礎知識(全5回)
- 動画
-
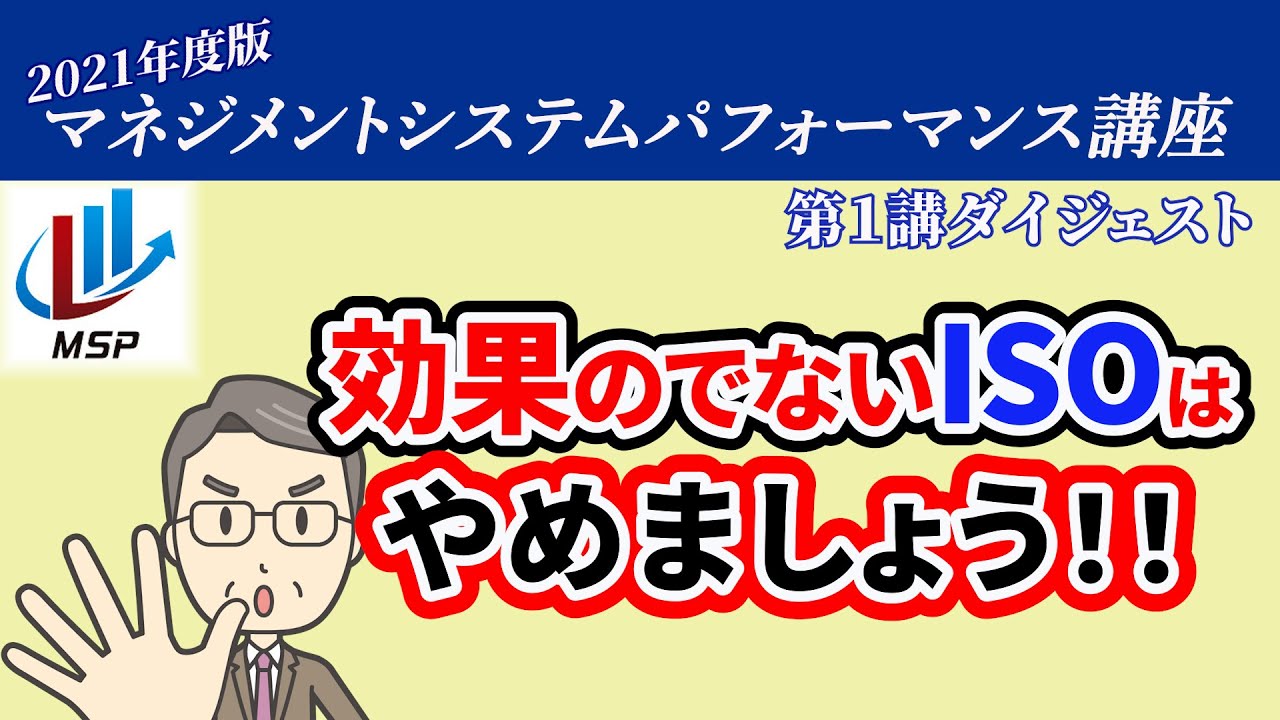
【MSP】2021年度マネジメントシステムパフォーマンス講座ダイジェスト(第1回)
- 動画
-

【SDGs】いまさら聞けない!SDGs(全5回)
- 動画
-
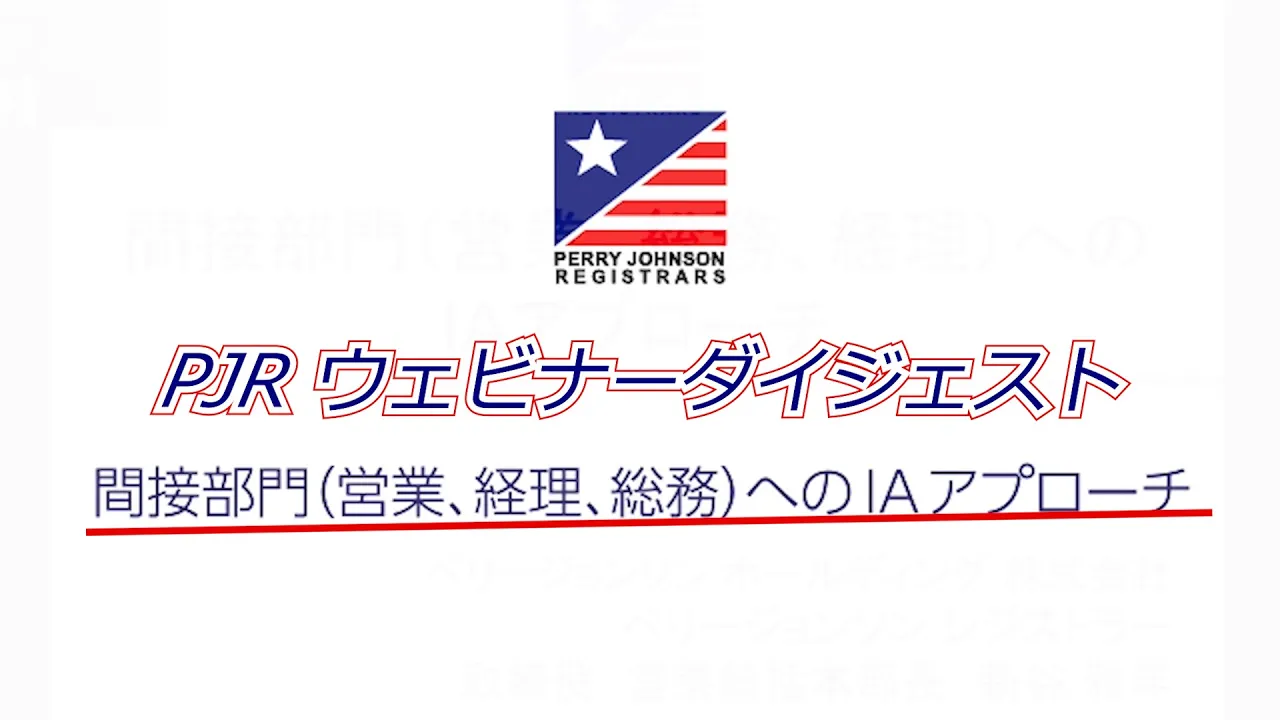
『間接部門へのIAアプローチ』2021年1月ウェビナーダイジェスト
- 動画
-

『IATF16949規格認証取得のポイント-TS16949からIATF16949へ』2018年4月ウェビナーダイジェスト
- 動画
-

『SDGsとマネジメントシステムの有効活用』2022年1月ウェビナーダイジェスト
- 動画
-
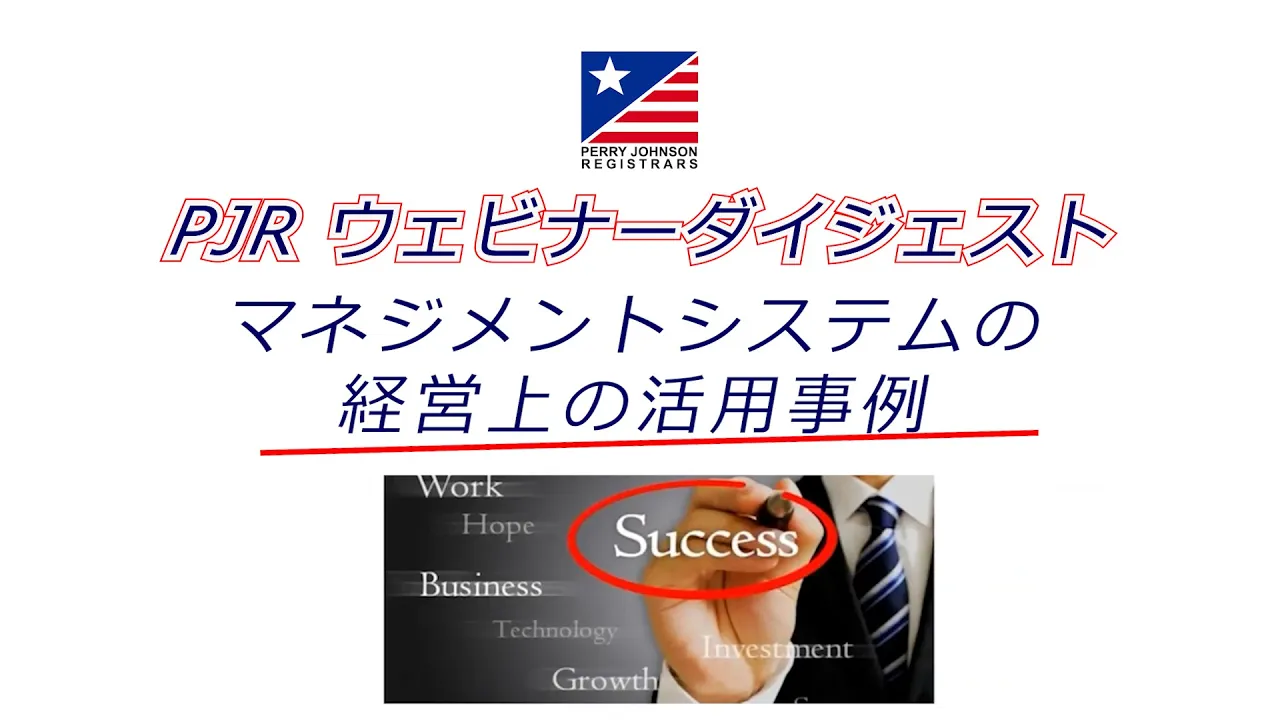
『マネジメントシステムの経営上の活用事例』2022年2月ウェビナーダイジェスト
- 動画
-

【IATF16949】『自動車産業と品質管理~品質管理の歴史とIATF発行の背景~』(全5回)
- 動画
-

【MSP】2023年度マネジメントシステムパフォーマンス講座(全7回)
- 動画




