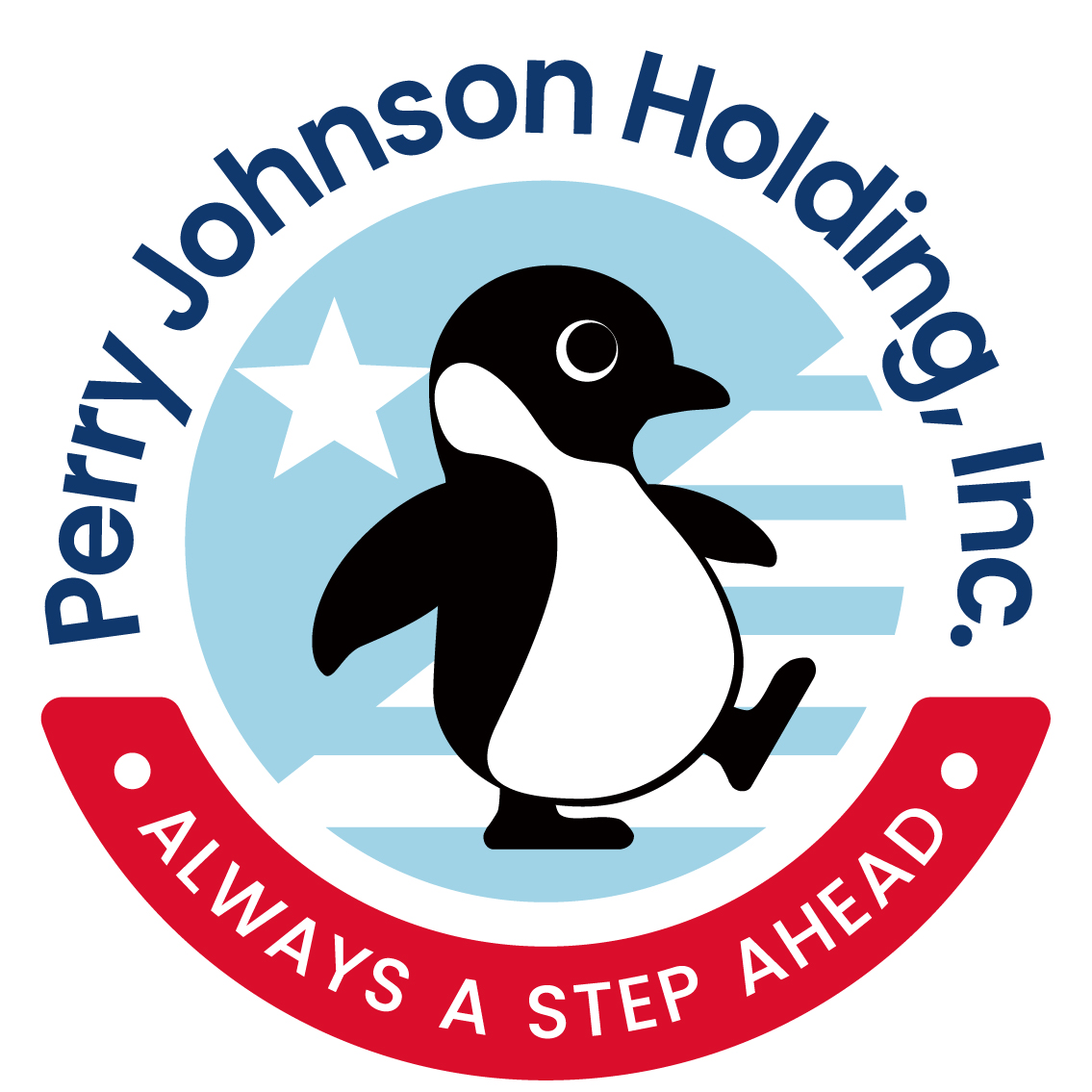コンテンツ
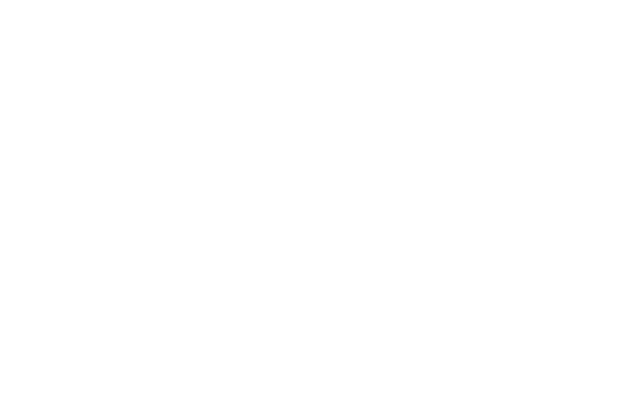
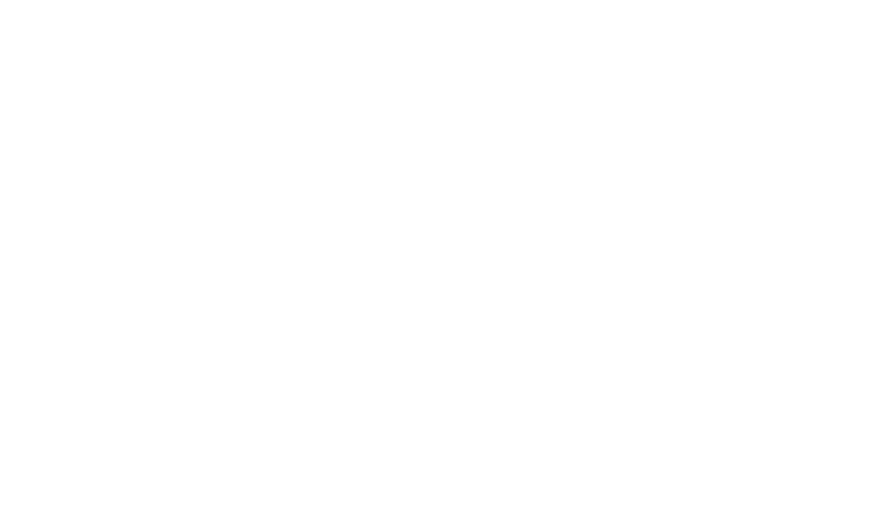
-
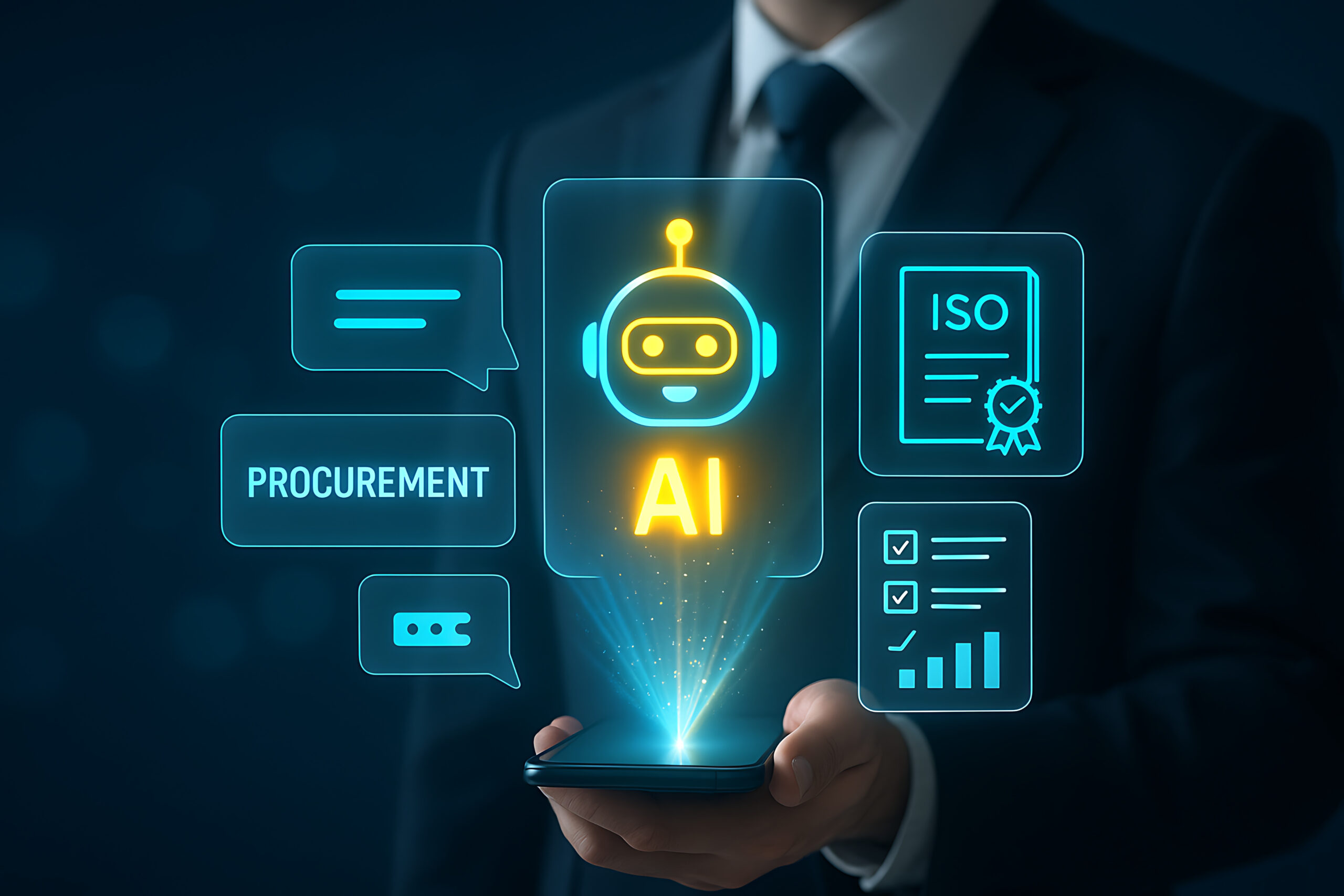
ISO 9001規格改訂×生成AIが導く次世代の品質マネジメント
- コラム
-

生成AI×ISOコラム~後編~ AI×マネジメント最前線―信頼を築くためのISO活用術
- コラム
-

生成AI×ISOコラム~前編~ 導入が進む海外と日本の課題―生成AIで差がつく時代へ
- コラム
-

PJRの審査料金、とてもお得ってご存じですか?
- コラム
-

【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~関係性管理~」(全6回)
- 動画
-
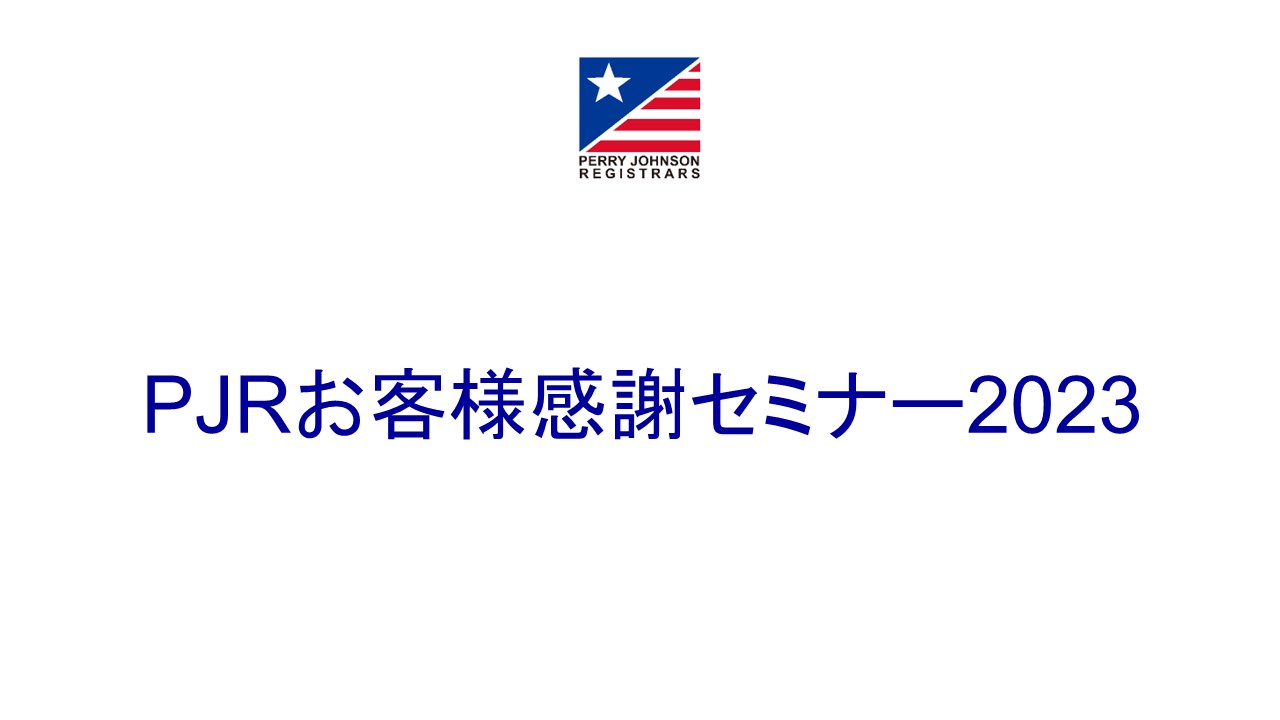
PJRお客様感謝セミナー2023
- 動画
-

保護中: 限定公開動画:サステナビリティ関連
- 限定公開動画
-

保護中: 限定公開動画:コンプライアンスセミナー関連
- 限定公開動画
-
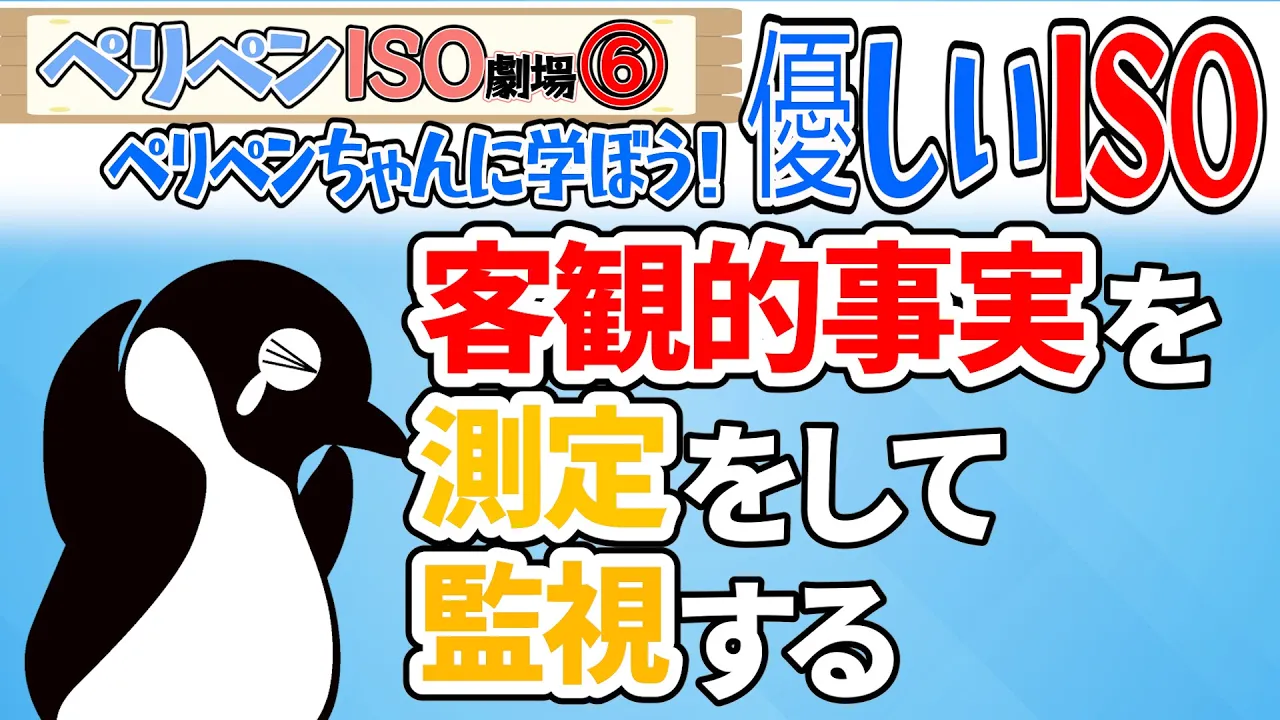
【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~客観的事実に基づく意思決定~」(全6回)
- 動画
-

【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~改善~」(全7回)
- 動画
-
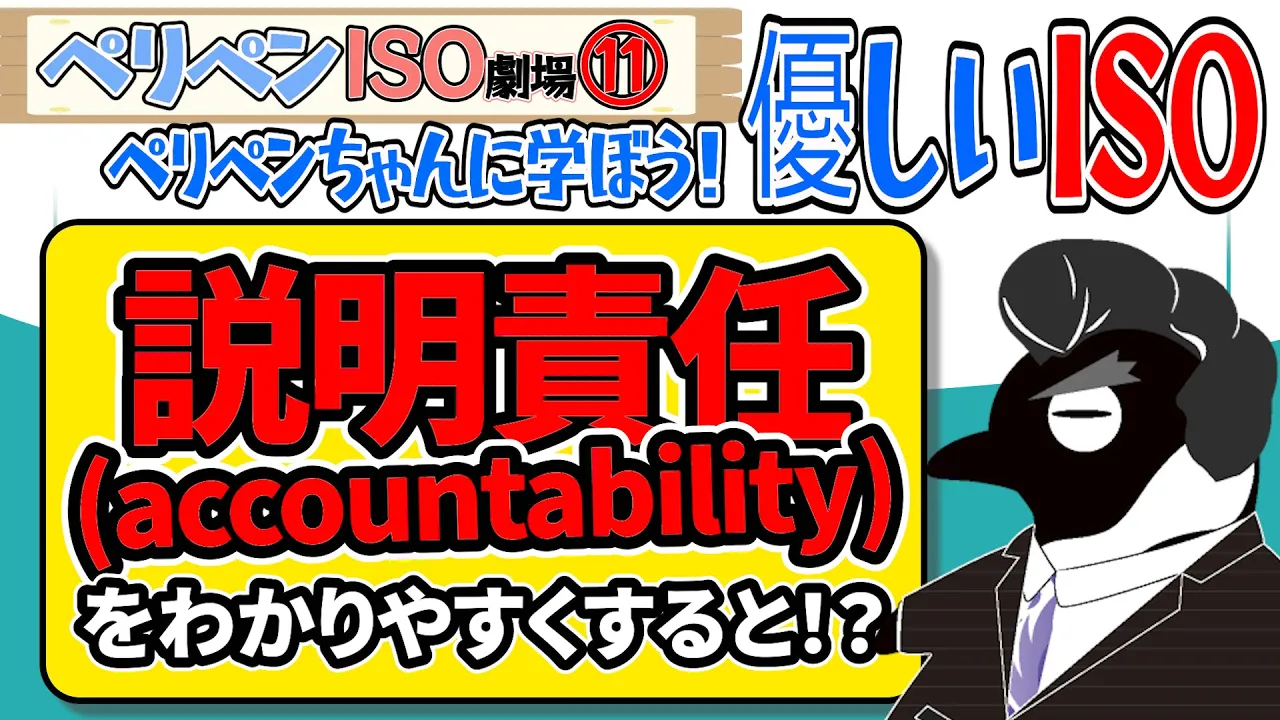
【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~プロセスアプローチ~」(全7回)
- 動画
-
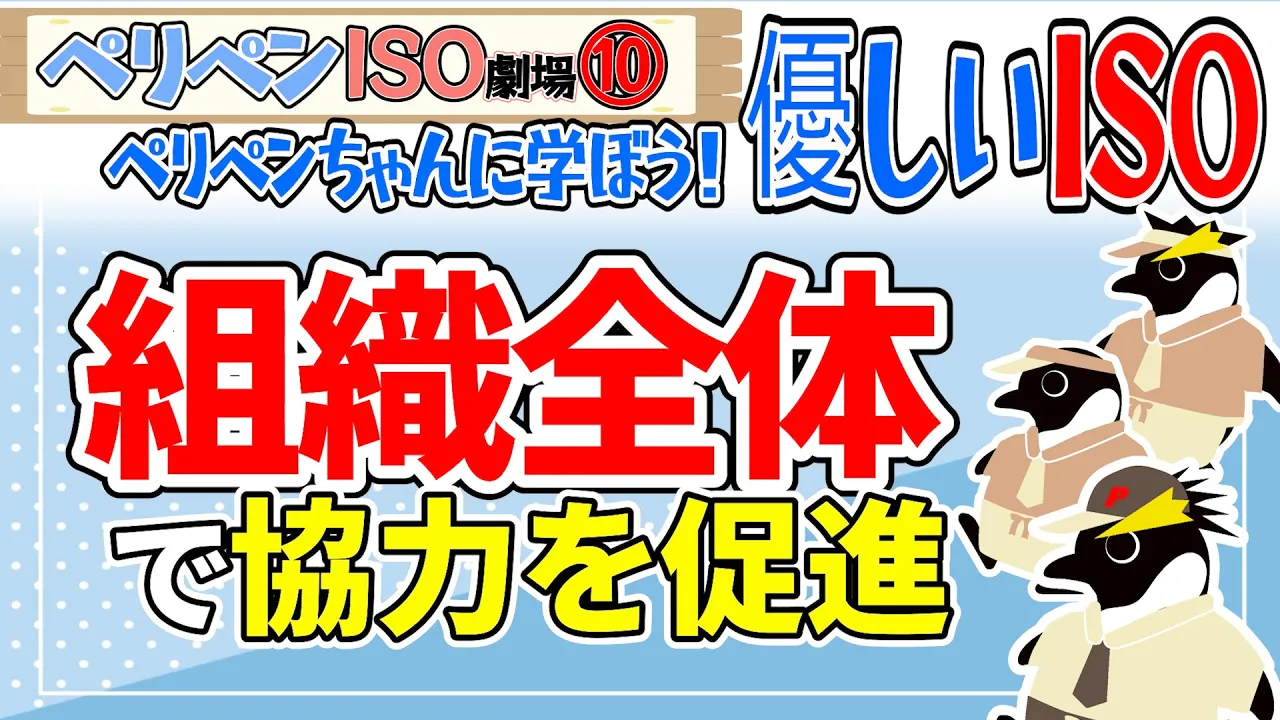
【ISO】品質マネジメントの7原則を分かりやすく解説「ISO劇場~人々の積極的参加~」(全7回)
- 動画