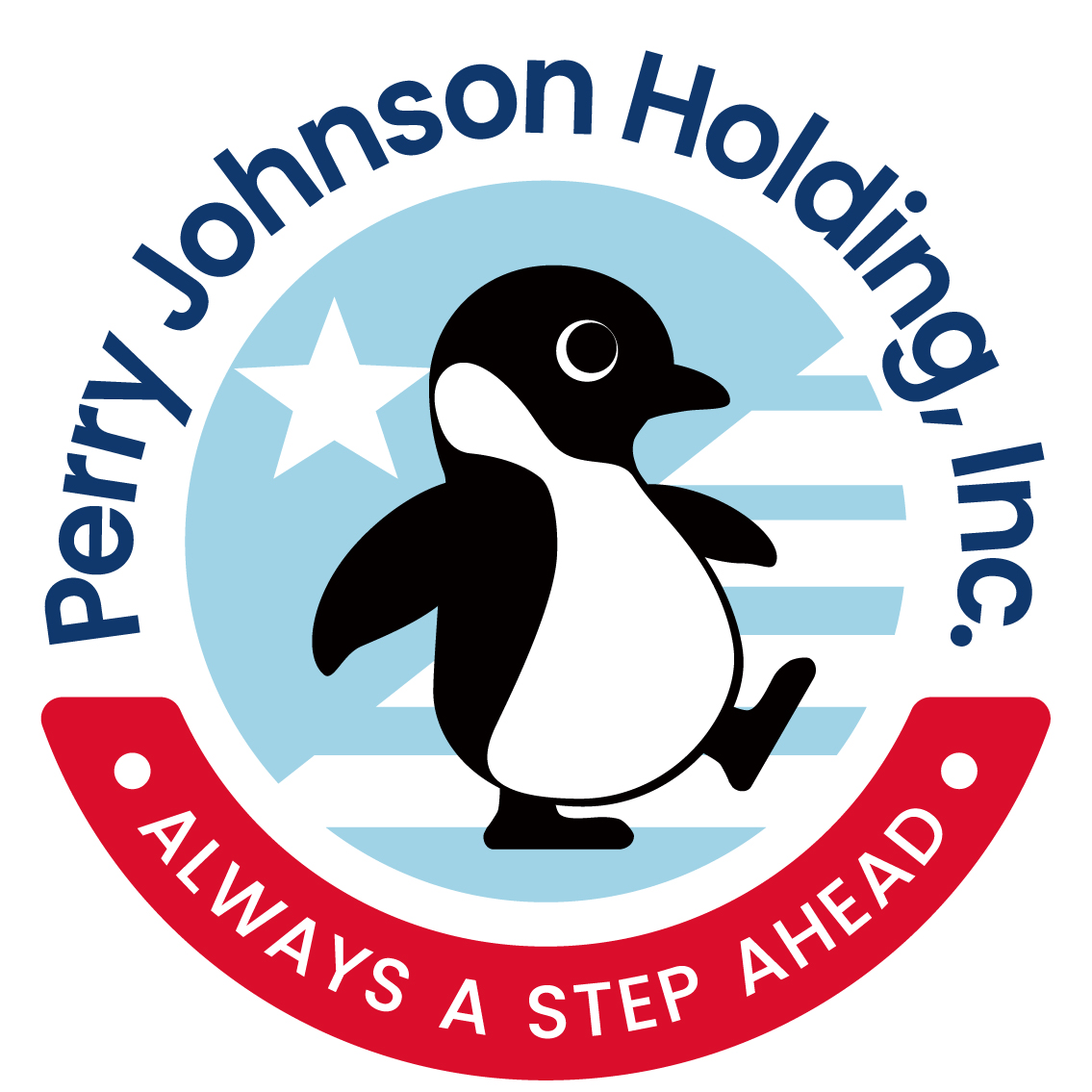- コラム
生成AI×ISOコラム~後編~ AI×マネジメント最前線―信頼を築くためのISO活用術

公開日:2025年9月12日
生成AIを安全かつ効果的に活用するには
生成AIの急速な普及に伴い、その安全性や信頼性を確保するための組織的な取り組みが求められるようになりました。こうした中、注目を集めているのがISO認証の取得によるガバナンス強化です。たとえば、次のようなISO規格に基づいて組織運営を実践することで、生成AIを安全かつ効果的に活用するためのルールや基盤の整備が可能になります。
・ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)
・ISO/IEC 42001(AIマネジメントシステム:※策定進行中)
・ISO 9001(品質マネジメント)
特に、情報管理のルールが曖昧なまま生成AIを導入すると、内部統制が機能せず、信頼を失ってしまうリスクもあります。ISO認証の取得は、こうしたリスクを最小限に抑え、自信をもって新たな技術を導入するための「安全弁」となります。
自治体においても、AI導入による業務改善やDX推進と併せて、ISO 37101(持続可能な開発に向けた地域運営)やISO 27001といった認証の活用が重要になります。これにより、住民からの信頼性や説明責任の担保につながります。
今後は、「生成AIを使うかどうか」ではなく、「どのように使いこなし、どのように社会や顧客の信頼を得ていくか」が重要な経営戦略になる時代です。生成AIとISOの両輪で、より強く、信頼される組織を目指していきましょう。
生成AIがもたらすマネジメント変革
私たちが日々取り組んでいるマネジメントシステムの業務に、生成AIをうまく活用することはできないのでしょうか?
実は、生成AIはこうした業務と非常に相性の良い技術だと感じています。というのも、情報をルールに沿って整理し、わかりやすく提示する――そういった作業において、生成AIは本領を発揮するからです。
たとえば、マネジメントシステムにおける次のような業務では、生成AIを実用的に取り入れることができると考えられます。
・内部監査計画やチェックリストのドラフト作成
・是正処置報告書の初期草案の生成
・顧客苦情や監査指摘事項の傾向分析
・文書レビュー時の文言の統一や抜け漏れチェック
・手順書や作業標準書のテンプレート生成
こうした業務は、定型的かつ文書ベースで行われることが多いため、ルールに沿って情報を整理・提示する生成AIの特性と非常に相性が良いのです。
生成AIは有効だが「丸投げ」はいけない
もちろん、生成AIは万能ではありません。最終的な判断や価値の見極めは、あくまで人間が担うべきものです。生成AIは、それをサポートする “アシスタント”として活用することが基本のスタンスになります。大切なのは、人とAIの役割を明確に分けたうえで、両者が共存できる仕組みをつくることだと言えます。
生成AIは今後ますます進化し、私たちの働き方や品質マネジメントのあり方にも大きな影響を与えることが予想されます。だからこそ、「難しそう」と敬遠するのではなく、まずは小さな一歩を踏み出してみることが重要です。その積み重ねが、次の時代の業務効率化や品質向上へとつながっていくでしょう。
生成AI×ISOコラム~前編~ 導入が進む海外と日本の課題―生成AIで差がつく時代へ はこちら
※本コラムは、PJRニュースレター「WORLD STANDARDS Review」に掲載された記事を再編集したものです。